
日本よりも台湾で知名度が高く、
特に年配の人への知名度は抜群。
しかも、
台湾の教科書でも紹介され、
「台湾の恩人」と称される、
八田 與一(はった よいち)とは、
いったいどんな人物で、
どんな人生を歩んだのかを
分かりやすく紹介します。

日本よりも台湾で知名度が高く、
特に年配の人への知名度は抜群。
しかも、
台湾の教科書でも紹介され、
「台湾の恩人」と称される、
八田 與一(はった よいち)とは、
いったいどんな人物で、
どんな人生を歩んだのかを
分かりやすく紹介します。

上杉景勝を生涯支え続け、
前田慶次とも仲が良かった、
直江兼続。
上杉家9代藩主、
上杉 鷹山(うえすぎ ようざん)の代に、
財政破綻寸前の窮地に追い込まれた
米沢藩を救う指針となった、
直江兼続が実施した方法とは?
また、
最後に直江兼続の負けず嫌いの性格を表した、
江戸城の廊下で
伊達政宗とすれ違った際のエピソードなど、
魅力たっぷりの直江兼続を紹介します。
最近では、
中村天風の考え・活動に
影響を受けた人物として有名な、
●MLBのロサンゼルス・エンゼルス所属のプロ野球選手
2021年 シーズンMVPとシルバースラッガー賞を受賞
2023年 ワールド・ベースボール・クラシックで活躍
2023年 シーズン
日本人およびアジア人史上初となる最多本塁打を獲得
大谷翔平選手が、
所属するロサンゼルス・エンゼルスに寄贈し、
パフォーマンスとして、
ホームランを打った選手の頭に被せるカブトは、
上杉景勝の腹心で、
前田慶次とも仲の良かった、
直江兼続のシンボル「愛」がついたカブトです。
この直江兼続のシンボルマークとなっている、
「愛」の字を前面につけた飾りのある兜の誕生秘話を
合わせて、紹介します。
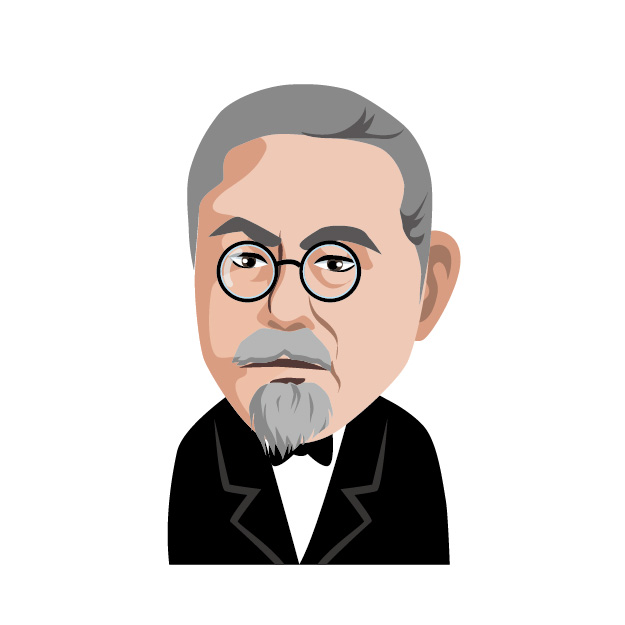
岐阜県で遊説中に暴漢に刺され負傷した、
あの有名人を診察したり、
台湾総督の補佐役として活躍後、
すごい役職を歴任し、
関東大震災後、
世界最大規模となる驚きの帝都復興計画を立案した、
後藤新平を紹介させていただきます。
後藤新平を紹介させていただきます。
後藤新平は、
有名なあの会社の名付け親だそうです。
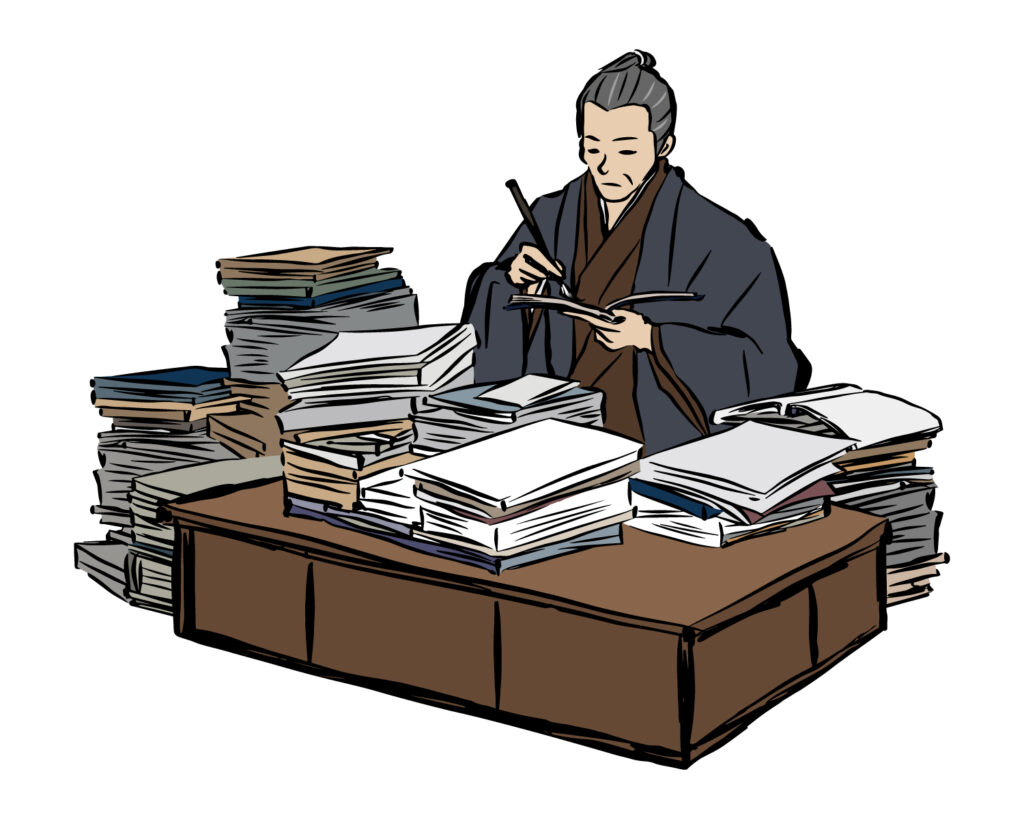
蘭学書の翻訳を日本で初めて試み、
大きな成果を上げた、
高野長英。
とあることがキッカケとなり、
顔の印象を変えるためにとった
驚きの行動に唖然!
そんな高野長英を紹介します。

豊臣秀吉から三顧の礼で迎えられ、
黒田官兵衛の子、
黒田長政を一計を案じ救った、
天才調略士、
竹中半兵衛の生涯と名言を紹介します。

武田信玄ではなく、
もし、
今川義元が山本勘助を雇っていたら、
「桶狭間の戦い」の結果だけでなく、
歴史が大きく変わっていたかもしれません。
今川義元が
山本勘助を雇わなかった2つの理由や
浪人から大活躍し、
守護神のようだとあがめられた、
そんな山本勘助の生涯を紹介します。

「巌流島の合戦」で有名な宮本武蔵
29歳まで、
約60回の勝負を行い、
なんと無敗と伝えられています。
その強さの理由とは?
また、
宮本武蔵の代名詞とも言われる「二刀流」
その「二刀流」で
「木刀」を使うことになった理由とは?
宮本武蔵といえば、
やはり佐々木小次郎との対決である、
「巌流島(がんりゅうじま)の決闘」
なんと、
この決闘の行われた時期について
いろいろな説があるだけでなく、
しかも、
9つものシナリオがあり、
今回2つだけ紹介します。
人気の高い、服部半蔵の生涯と名言を
分かりやすく解説させていただきました。

身長が戦国時代ナンバー1の忍者と名高いだけでなく、
伝えられている容姿がものすごい!
ミステリアスな忍者、
風魔小太郎の生涯を紹介します。
相模国小田原(現在の神奈川県小田原市)に
居城を構えていた、
後北条氏(ごほうじょうし)
5代将軍の北条氏直に仕えた
忍者集団のトップであったと思われます。
伝えられている、
身長と容姿と戦い方がすごいと
伝えられています。
大活躍をした風魔小太郎率いる忍者集団ですが、
豊臣秀吉の「小田原攻め」により、
主君、北条氏直を失い、
最後は、
江戸の奉行所による「盗人狩」が行われ、
江戸近辺を荒らしまわっていた盗賊が
根絶やしにされ、
その中に風魔小太郎もいたと推測されています。
そんな、
風魔小太郎の生涯を
分かりやすく解説させていただきました。

非常に不利な状況からの、
あの有名な「●●越え」で、
徳川家康をピンチから救い、
「日本の忍者ランキング」で必ず上位に上がる、
服部半蔵の生涯と名言を紹介します。

様々な理由から、
合計6人もの主人に仕えることとなった、
島左近。
6人目の主人、
石田三成に雇われる際の内容に驚きです。
そして、1600年、
「関ヶ原の戦い」の本戦が幕を切って落とされ、
当初は石田三成率いる、
西軍が有利に戦を進めます。
「関ヶ原の戦い」では、
島左近も自ら陣頭に立ち大活躍、
島左近の戦いぶりは、
徳川方でも有名となり、
『誠に身の毛も立ちて汗の出るなり』と
恐れられたことが、
伝えられています。
しかし、この戦いにより、
61歳でその生涯を閉じることとなります。
そんな、島左近には、
なんと最後の死亡説と生存説で、
それぞれ3つずつあるという、
本当にミステリアスな人物となります。
そんな、ミステリアスな人物、
島左近の生涯と名言を紹介します。
最近のコメント